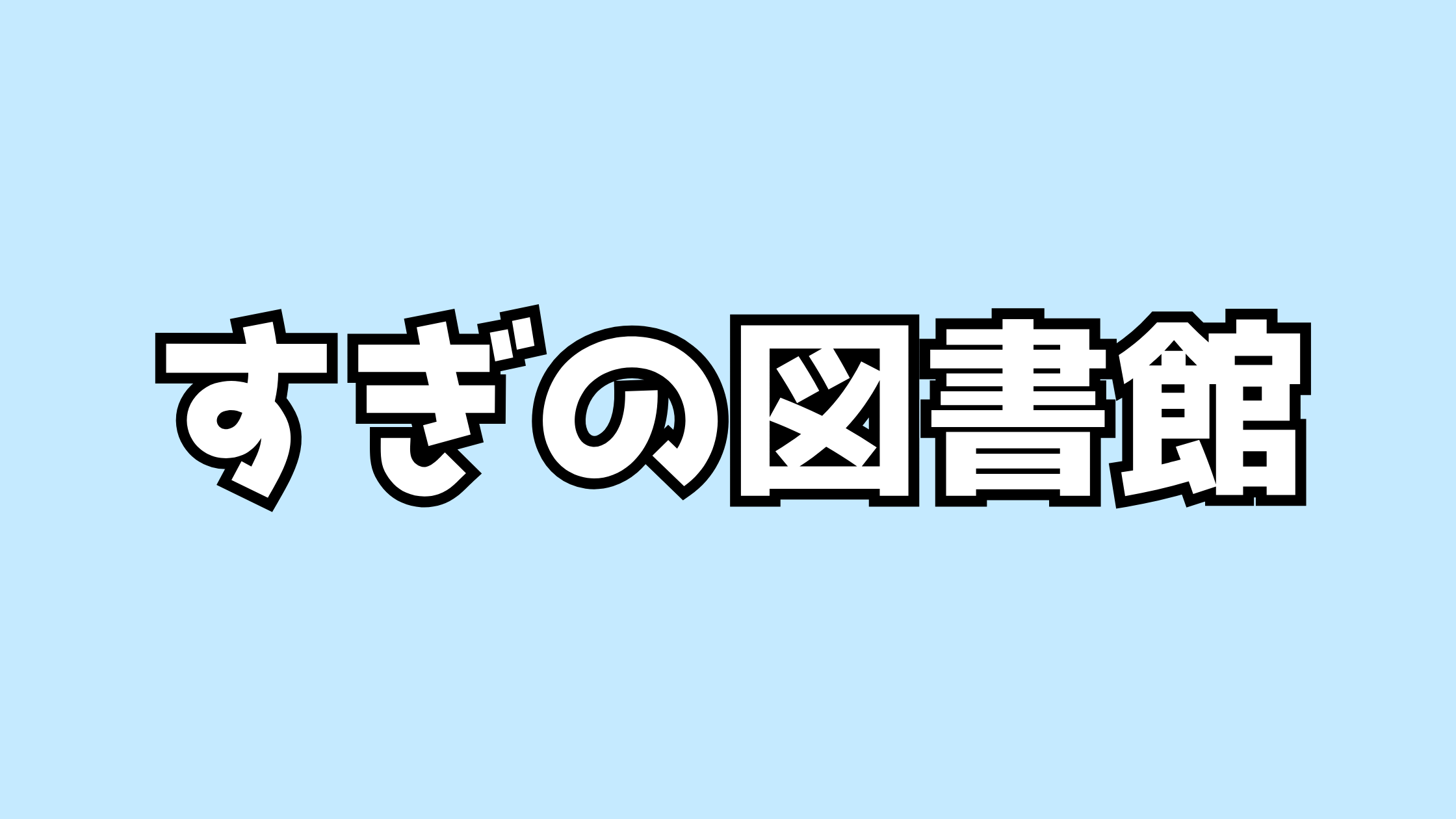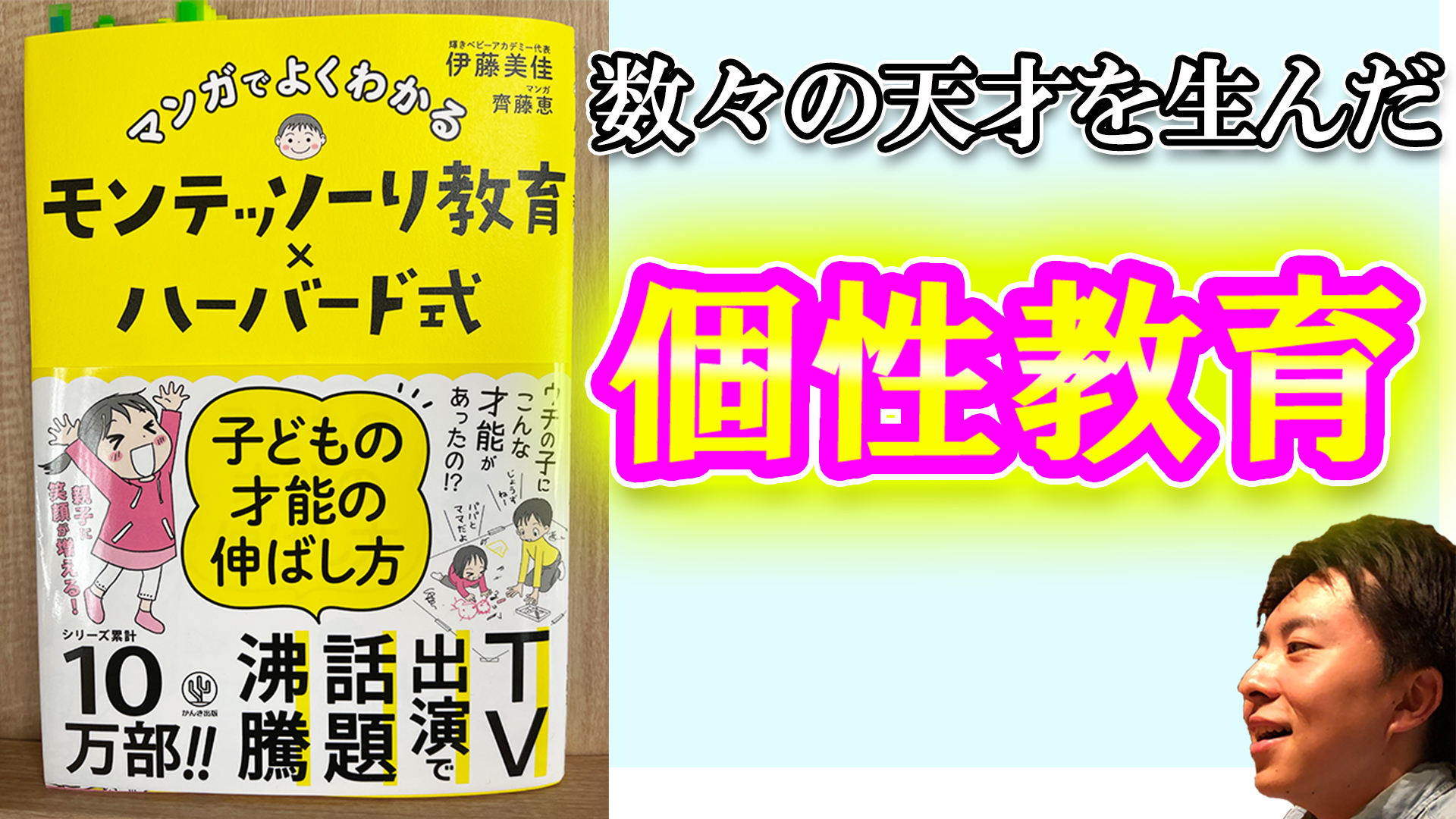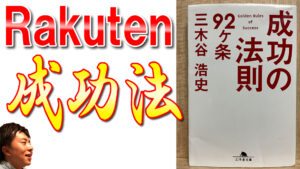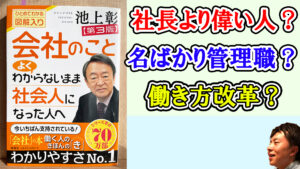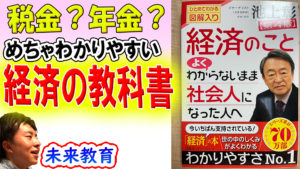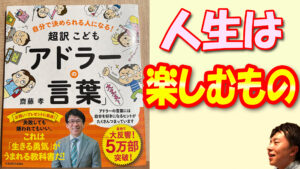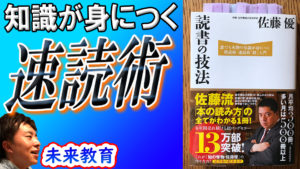伊藤美佳さんが書かれた本《漫画でよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子供の才能の伸ばし方》の、読書感想についてお話します。
伊藤美佳さんは幼稚園・保育園・スクールで28年間、2万人以上の子供達と関わってきた方で、教育関係の免許を持ち、メンタルカウンセリングのコーチでもあります。
まず、モンテッソーリ教育とは何かというと、子供の個性(才能)を開花させる教育のことです。
幼少期にこのモンテッソーリ教育を受けた有名人がいます。
・藤井聡太さん(将棋棋士)
・バラク・オバマ(前アメリカ大統領)
・ジェフ・ベゾス(Amazon創設者)
・ラリー・ペイジ(Google創設者)
・マーク・ザッカーバーグ(facebook創設者)
このように日本では今話題の藤井聡太さんや、世界トップの大手企業GAFA(Google、Apple、facebook、Amazon)の創設者3人が子供の頃に受けていた教育です。
これらの教育は先生に教えてもらうわけではなく、親が子供に行う教育です。
この本はイラストが多く、わかりやすく書かれています。
お子様を藤井聡太さんのように、個性を伸ばす教育をしたい方はお読みいただければ幸いです。
9つの能力
①【体】の知能:運動神経
②【言葉】の知能:表現力
③【数】の知能:論理的思考、プログラミング思考
④【絵】の知能:クリエイティブ思考
⑤【自然】の知能:感受性
⑥【感覚】の知能:センス
⑦【音楽】の知能:リズム感
⑧【人】の知能:コミュニケーション
⑨【自分】の知能:志(夢、目標)
ハーバード大学のガードナー教授は“人にはIQ以外の9つの知能があるよ”と言います。
この9つの知能のことです。
これらは子供によって得意・不得意がバラバラなので、子供に合った教育が必要です。
1歳~4歳までの子供を育てているお母さん達がこの9つの知能を育てるモンテッソーリ教育を実践したところ、「自己肯定感が上がって夫婦関係が良くなった!」とか「1歳の子供が夕飯作りを手伝ってくれる!」など、お母さん達の幸福度も上がったそうです。
子供のイタズラは成長の合図
イタズラは成長の証
伊藤さんは子供が床や壁に絵を描いたり、物を投げたりするのは”成長のサイン”だと言います。
イタズラに対して「止めなさい!」と注意すると、9つの知能の成長を妨げることになります。
9つの知能を伸ばすためには、大きい紙とペンを渡して、「ここに絵を描こうね」と遊び方を教えることが大切です。
また、何かを投げる時は想像力を働かせてごっこ遊びをしているので、柔らかいボールと人形などの当てるモノを用意して遊ばせることが大切です。
絵を描いたり、ごっこ遊びなどで想像力を育てることによって、デザインや音楽などクリエイティブな能力が高まります。
また『イタズラ=成長』と理解していれば、お父さん&お母さんのストレスも無くなります。
イタズラの意味を理解していないと注意することに疲れるし、子供も自己肯定感が低くなり、学校や会社でコミュニケーションが取れずに苦しむ人生になります。
イタズラは9つの知能を自ら伸ばしている時です。
「私を困らせようとしてる!」という思い込みで怒ることは止めて、成長を喜びましょう。
親子の信頼
好きなことをどんどんやらせる
子供に「止めなさい!」と注意ばかりしていると、親子の信頼関係が悪くなり、さらに自己肯定感の低い人になってしまいます。
自己肯定感の低い大人になってしまうと、職場でイジメられてうつ病になり、社会復帰できなくなったり、最悪は命を落とすこともあります。
伊藤さんは“好きなことをどんどんやらせてください”と言っていて、好きなことをやらせてもらえた子供は、お父さんとお母さんを信頼します。
また、遊んでいるうちに飽きてしまい、別の遊びに興味を持つことがありますが、それも”どんどんやらせてください!”と。
好きなことをさせていれば、ワガママにはならず、親に感謝してお手伝いをしたり、コミュニケーション力の高い人に育ちます。
また親が子供の行動を認めることによって、集中力も鍛えられます。
集中力は勉強や会話など、人間には大切な力です。
良い人に育てようと注意ばかりしていると、臆病になって隠す癖がついたり、他人を騙すような悪い人になってしまいます。
成功体験が自信になる
いろんなことにチャレンジさせて、やり抜く力を鍛える
「止めなさい!」ではなく、好きなことを認めてあげることによって、自信のある人に育ちます。
自信のある人はやり抜く力が高く、勉強、スポーツ、音楽など、何でもチャレンジして成功する人になります。
世の中には「お金持ちになりたい!」「幸せになりたい!」と言う人が多いですが、これらの夢を叶えるためには、やり抜く力が必要です。
やり抜く力に関しては、アメリカで子供の貧困と教育政策を専門に活動しているポール・タフさんの成功する子 失敗する子 何が「その後の人生」を決めるのかにも書かれています。
やり抜く力が低い人は、パチスロなどのギャンブルや、ソシャゲのガチャでお金を使い込んでしまってお金に困る人生になりやすくなります。
また、仕事や結婚生活などで嫌なことがあれば逃げてしまい、何も上手くいかない幸せではない人生になります。
そのために子供には好きなことをやらせて、たくさんの失敗をさせて、失敗を乗り越える『自信のある人』に育ててあげてください。
自分で選ばせる
子供に選ばせる
“遊びや玩具を子供に選ばせてあげてください”と伊藤さんは言います。
人生は、友達/仕事/結婚相手/資格/趣味など、自分で選ばないといけないことがたくさんあります。
結婚を考えている人から「お母さんに聞かないと…」なんて言われたら、不安になりますよね。
選ぶ力が弱いと、学校や会社で嫌なことがあったときに、命を落とすこともあります。
選ぶ力があれば、「変なことを言う奴は無視しよう!」や「他の会社に転職しよう!」と、生き抜くための判断ができます。
なので、玩具や本など何でも親が選ぶのではなく、子供に選ばせてあげることが大切です。
選んだことに対して失敗すれば、「なぜ失敗したか?」「次はどうしたら失敗しないか?」という論理的な思考が鍛えられます。
将棋棋士の藤井聡太さんや。オバマ前大統領がパッと考えられるのは、この論理的な思考が高いからです。
藤井聡太さんは、1日も早く将棋棋士になるために「高校の卒業はいらない」と判断して中退しました。
藤井聡太さんのように自分の時間を有意義に使う判断、またオバマ前大統領のように多くの人が幸せになる判断ができる人になるためには、子供のときから選ぶ力を鍛えることが大切です。
おわりに
現代ではモンテッソーリ教育やシュタイナー教育など、様々な個性(才能)を育てる教育機関が世界中で増えています。
それは世界中の働き方が、人からAIロボットに切り替わっているからです。
このAIを活用するスキルを学べる教育が、モンテッソーリ教育やシュタイナー教育といった学校教育とは異なる性格(個性)教育です。
今の日本の学校教育は、約150年前の明治時代に生まれた教育です。
この時代は産業が発達し、自動車の工場ラインやデパートなどでたくさんの人を雇うために、雇われる人の教育が必要でした。
学校では「皆と同じことをしなさい」という、上司の指示通りに動くロボットを作るような教育が続いています。
テクノロジーが発達すると、無くなる仕事やモノは必ず出てきます。
過去にも馬車は自動車に、洗濯板で洗濯する人は洗濯機に、予約窓口は予約アプリなど、たくさんの仕事が時代の変化によって消えていきました。
子供の人生を決める性格教育は学校の先生ではなく、親です。
僕が他にオススメする本は厳選|すぎの先生のオススメ本にまとめてあります。